国民健康保険料の軽減・減免 制度簡単解説
9/29/2025 9/29/2025
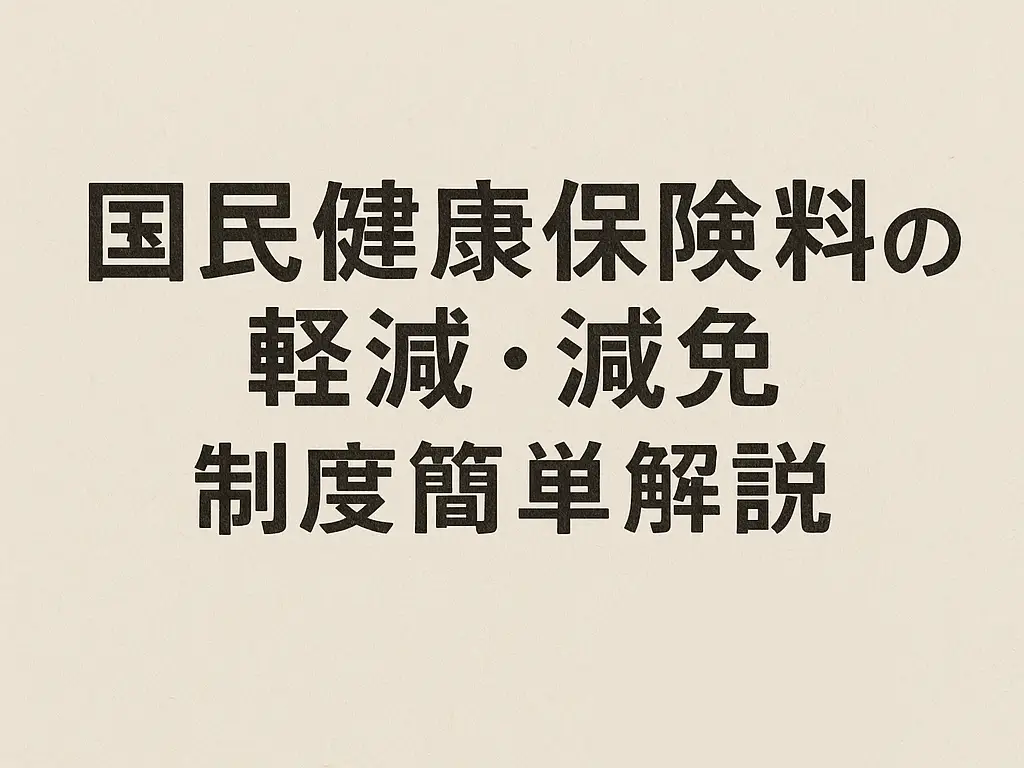
収入が不安定になったり、家計が厳しくなると、毎月の国民健康保険料は大きな負担に感じます。そんなときにまず知っておきたいのが、全国共通の「軽減・減免」制度です。条件を満たせば、自動で減額されるものから申請で負担を抑えられるものまで、いくつかの仕組みがあります。
この記事では、要点だけサッとつかめるように制度の骨子と対象者をまとめました。
制度の概要
国民健康保険料の軽減・減免は主に次のとおりです。
法定軽減(7割・5割・2割)
前年所得が一定基準以下の世帯は、均等割・平等割が自動的に減額されます(毎年度判定・所得申告がないと適用漏れに注意)。
未就学児の均等割 半額(全国一律)
2022年4月開始。世帯の所得にかかわらず、未就学児に係る均等割が5割軽減されます(手続き不要・自動)。
産前産後の保険料免除(全国一律)
2024年1月施行。出産する被保険者の産前産後4か月分(多胎は6か月分)の所得割・均等割が免除されます(届出が必要。出産85日以上が対象)。
非自発的失業(倒産・解雇・雇止め等)特例
離職日の翌日から翌年度末までの期間、前年の「給与所得」を30%としてみなすことで保険料負担を軽くします(65歳未満・雇用保険の特定受給資格者/特定理由離職者・届出必要)。
災害減免(申請)
地震・風水害・火災などで生活基盤に大きな被害を受けた場合、被害割合や所得に応じて部分~全額の減免が認められることがあります(自治体基準)。
所得減少による減免(申請)
自己都合退職や廃業・病気などで所得が大きく落ちた年、基準に合えば**所得割の40~80%**等の減額が設定されます(自治体ごとに細目あり)。
旧被扶養者の特例(後期高齢者医療への移行に伴う)
被用者保険の被扶養者だった65~74歳の方が国保に入るケースで、所得割は全額免除、均等割・平等割は2年間半額などの経過措置(申請)。
注:
名称や細かな計算式・書類は市区町村で異なります。必ずお住まいの自治体ページで最新情報をご確認ください。
対象者(要約)
| 制度 | 主な対象・要件 | 期間・手続き |
|---|---|---|
| 法定軽減(7割/5割/2割) | 前年の世帯所得が国の基準以下 | 毎年度。原則自動(要所得申告)。 |
| 未就学児の均等割 半額 | 国保加入の未就学児(所得不問) | 通年。自動適用。 |
| 産前産後免除 | 出産する被保険者(妊娠85日以上。死産・流産等含む) | 単胎4か月/多胎6か月。届出必要。 |
| 非自発的失業特例 | 65歳未満・「特定受給資格者/特定理由離職者」等 | 離職翌日~翌年度末。届出必要(雇用保険受給資格者証等)。 |
| 災害減免 | 住家・家財等の損害が一定割合以上 等 | 被害月以降の保険料。申請(罹災証明等)。 |
| 所得減少減免 | 前年比で大幅減(例:30%以上)かつ所得水準が基準以下 | 当該年度。申請(収入見込書・退職/廃業の証明等)。 |
| 旧被扶養者特例 | 被用者保険の被扶養者→国保加入の65~74歳 | 所得割全額免除+均等/平等割2年半額。申請。 |
申請が必要なケースの主な書類例
雇用保険受給資格者証/罹災証明書/退職・廃業の証明/収入見込額の申告書/母子健康手帳 等(自治体で案内あり)。
まとめ
国保の軽減・減免は、「低所得の自動軽減」「子育て・出産の全国一律の配慮」「失業・災害・急な減収への申請型」と大きく3系統。まずは自分がどれに当てはまるかを確認し、申請が必要なものは早めに手続きを。制度の柱や開始時期(未就学児半額は2022年、産前産後免除は2024年)は全国共通ですが、細部は自治体ごとに異なります。公式の最新案内(厚生労働省・お住まいの市区町村)をチェックして、ムダなく負担を軽くしましょう。
<健康保険法・厚生労働省>
https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21517.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001062618.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004oa7.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html